近年、電気自動車(EV車)やハイブリッド車の普及に伴うガソリン税の減収や道路インフラの維持費確保のために、新たな税制として「走行距離税(走行税)」の導入が検討され、議論が進められています。
この税制度が導入されると、ガソリン車だけでなく電気自動車などのすべての車が走行距離に応じて課税される可能性があります。
そのため、実際の導入時期や課税の仕組み、税負担の増加などについて、疑問や不安を持つ人も多いのではないでしょうか。
本記事では、走行距離税の基本的な仕組みや課税方法、日本での導入時期、走行距離税の導入によるメリット・デメリットを詳しく解説します。
走行距離税(走行税)とは?

走行距離税(走行税)とは、車が走行した距離に応じて課税される新たな税制度のことです。
現在の日本では、燃料購入時に課される「ガソリン税」や「軽油引取税」が道路整備の財源となっています。しかし、電気自動車やハイブリッド車の普及により、燃料消費が減少し、それに伴い税収の減少が懸念されています。
この状況を補うために、走行距離に応じて課税する「走行距離税(走行税)」の導入が検討されています。
この制度が実際に導入されると、ガソリン車に限らず、電気自動車や燃費の良い車にも走行距離に応じた負担が求められる可能性があります。
なぜ今、走行距離税が注目されているのか
走行距離税が注目されている理由の一つは、ガソリン税収の減少です。
ガソリン税は、日本の道路整備や維持管理のための主要な財源ですが、電気自動車やハイブリッド車の普及によるガソリン車の減少は、ガソリン税収の減少に直結します。
また、現行の税制では、ガソリン車は燃料購入時にガソリン税を支払いますが、電気自動車はガソリンを使用しないため、この税負担がありません。そのため、電気自動車のユーザーは道路を利用しているにもかかわらず、道路維持のための税負担をしていないという不公平感が指摘されています。
走行距離税の課税方式

走行距離税は、車の走行距離に応じて税額が決まる仕組みです。
現行の燃料課税とは異なり、車種や燃費に関係なく、利用した分だけ負担するという考え方に基づいています。
ここでは、具体的な課税方式の違いについて解説します。
走行距離計による課税方式
走行距離税の課税方法には、いくつかの方法が考えられています。
まず、最もシンプルな方法として「車検時の走行距離を基に課税する方式」があります。
この方法では、車検の際にオドメーター(走行距離計)の数値を記録し、前回の車検時からの走行距離を基に税額を計算します。
この方法では特別な機器を追加する必要がないため導入コストが低い一方で、課税のタイミングが車検ごとになるため、一度に大きな負担が発生する可能性があります。
通信機能による課税方式
より精密な方法として「GPSや通信機能を活用したリアルタイム課税方式」も考えられています。
この方式では、車両に専用の通信機器を搭載し、走行距離をリアルタイムで記録・課税します。正確な走行距離が計測できる一方で、プライバシーの問題や、専用機器の導入コストが課題となります。
給油時に申告
上記以外の方法として「給油時に走行距離を申告する方法」も検討されています。
この方法では、給油の際に車の走行距離を記録し、それに基づいて税金を支払う仕組みです。しかし、申告の正確性を確保する仕組みや、給油のたびに計測する手間が課題となる可能性があります。
ガソリン税と走行距離税の違い

ガソリン税は、燃料を購入する時にその量に応じて課税されるため、燃費の良い車ほど税負担が軽くなります。一方、走行距離税は走行した距離に応じて課税されるため、燃費の良し悪しに関係なく、走れば走るほど税負担が増える仕組みです。
これにより、道路インフラの維持管理に対する負担を公平に分配できるというメリットが生まれます。
ただし、現行のガソリン税が廃止されずに走行距離税が導入される場合、ガソリン車にとっては二重課税となる可能性があり、導入に対して不安の声が上がっています。
海外での導入事例
燃料税に依存した道路維持費の確保が難しくなっていることから、海外では走行距離税の導入を進める国や地域が増えています。
電気自動車の普及が進む中で、ガソリン車との税負担の不均衡を解消し、公平な課税を実現するための手段として注目されています。すでに試験運用が行われている国もあり、日本でもこれらの事例を参考にしながら制度設計が検討されています。
アメリカのOReGOプログラム
アメリカのオレゴン州では「OReGO」というプログラムが導入されており、ドライバーが走行距離に応じて課税される仕組みを導入しています。
この制度では、車両にGPS機能を搭載した装置を取り付け、走行距離に応じて納税額が決まります。燃費の良い車や電気自動車が増加する中で、公平な税負担を目指す取り組みの一環として進められています。
ニュージーランドの道路利用車料
ニュージーランドでは「道路利用者料(Road User Charges、RUC)」という制度が導入されており、軽油を使用するすべての車両(ディーゼル車など)および一部の大型車に対して、走行距離に応じた課税が行われています。
この制度では、事前に走行距離分の料金を支払い、オドメーターの記録を基に管理される仕組みとなっています。
日本ではいつから走行距離税が導入される?
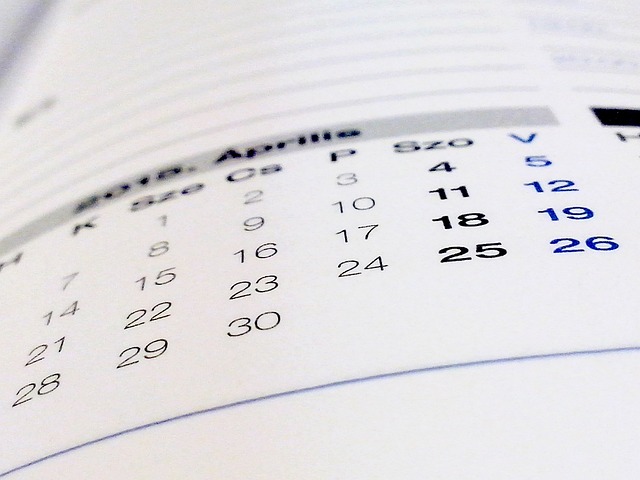
日本での走行距離税の導入時期については、政府や関係機関による議論が進められていますが、具体的な導入時期はまだ決まっていません。
ただし、電気自動車の普及が進む中で、従来のガソリン税収の減少が問題視されており、今後の税制改革の一環として導入される可能性は高いと考えられます。
政府は2050年のカーボンニュートラル目標に向けてEVシフトを推進しており、2035年には新車販売を電気自動車(電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車など)に限定する方針を打ち出しています。この流れの中で、ガソリン税収が減少することは避けられず、新たな財源として走行距離税の導入が現実味を増しています。
政府や関係機関の検討状況
政府や関係機関は、走行距離税の導入に向けた検討を段階的に進めています。
例えば、国土交通省はこれまでに「道路財源の確保に関する有識者会議」を開催し、将来的な税収確保の観点から、走行距離に応じた課税方式の導入を議論しています。また、財務省も税制改正の一環として、走行距離税の導入を含めた自動車関連税制の見直しを進める方針を示しています。
自動車業界からは否定的な意見も多い
走行距離税の導入について、自動車業界からは慎重な意見も多く、自動車ユーザーへの負担増や、正確な走行距離の計測方法について課題が指摘されています。
そのため、政府としては、導入の際にどのような方式を採用するのか、また現行のガソリン税との兼ね合いをどうするのかについて、慎重に検討を進めている段階です。
走行距離税のメリット

走行距離税の導入は、ガソリン車と電気自動車の公平な税体系が実現する、と期待されています。
電気自動車や燃費の良い車が増加し、従来のガソリン税が十分に機能しにくくなっている現状を踏まえると、より持続可能な税収確保の手段として有効であると考えられます。また、道路インフラ維持の財源確保や環境負荷の軽減にも寄与する可能性があるため、政府や関係機関は導入の検討を進めています。
電気自動車や燃費の良い車にも公平に課税できる
従来のガソリン税は燃料の消費量に応じて課税されるため、燃費の良い車や電気自動車を利用するユーザーは税負担が少なくなります。
もし走行距離税が導入されれば、車種や車両性能に関係なく、実際に走行した距離に応じて課税されるため、すべてのドライバーに公平な税負担を求めることが可能になります。
今後、電気自動車の普及によるガソリン税の減収が進む中、すべての車両に公平な課税を実現する手段として、走行距離税は有力な選択肢となります。
道路インフラ維持の財源確保
日本の道路は、高速道路や一般道を含め全国に広がっており、その維持管理には莫大なコストがかかります。現在はガソリン税や自動車税などが主な財源となっていますが、走行距離税を導入すれば、走行した分だけ課税されるため、ガソリン税収の減少による財源不足を補うことができます。
さらに、走行距離に応じて課税されるため、道路を多く使用した人がその維持費を多く負担する形となり、より公平な負担が実現できます。
車の利用抑制と環境負荷の軽減
走行距離税の導入は、結果的に車の利用を抑制し、環境負荷を軽減する効果も期待できます。
長距離移動が多い人ほど税負担が大きくなるため、不要な移動を控える動機付けとなり、渋滞の緩和や交通量の適正化につながる可能性があります。
CO₂排出量の削減にも寄与することが期待されています。自家用車の利用が減ることで、公共交通機関の利用が促進される可能性があり、全体としての環境負荷の低減につながると考えられます。
走行距離税のデメリット

走行距離税の導入には多くのメリットがある一方で、課題も少なくありません。
車を頻繁に利用する人への負担増加や、走行距離の計測方法に関するプライバシーの問題、既存の税金との二重課税の可能性など、慎重に議論すべき課題が多く存在します。
これらの問題を十分に考慮し、適切な対策を講じなければ、利用者の負担が過剰になったり、新たな社会的課題を生む可能性もあります。
車を多く利用する人の負担が増える
走行距離税は、実際に走行した距離に応じて課税される仕組みのため、交通インフラが整っていない地方に住んでいる人や仕事で車を使う必要がある人にとっては、税負担が重くなる可能性があります。
公共交通機関が充実している都市部では、電車やバスでの移動が可能なため、車の利用を減らす選択肢がありますが、地方では移動手段が限られており、通勤や買い物、病院への通院などで車を使わざるを得ない人が多いため、結果的に地方在住者の負担が大きくなる可能性があります。
走行距離の計測方法に関するプライバシー問題
走行距離を計測する手段として、GPSを利用した位置情報の記録や、車両の走行データを政府や関係機関が管理するシステムが考えられています。
しかし、これには個人の移動履歴が追跡されるリスクがあり、プライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
二重課税の可能性
日本ではガソリン税や自動車税など、車に関連するさまざまな税金が課されています。この状況で新たに走行距離税が導入されると、既存の税金との重複による「二重課税」の問題が発生する可能性があります。
特に、ガソリン税はすでに燃料の消費量に応じて課税される仕組みになっており、燃費の悪い車ほど多くの税金を負担しています。現在の税負担に加えて走行距離税が導入されると、ガソリンを消費する車に対して二重に税負担がかかることになります。
そのため、走行距離税を導入する際には、既存のガソリン税や自動車税とのバランスをどう取るのか、あるいはこれらの税制をどのように見直すのかが注目のポイントです。
まとめ

走行距離税は、実際の走行距離に基づいて課税される新たな税制であり、電気自動車の普及による税収減対策として注目されています。
公平な負担を実現できる一方、地方在住者や業務で車を使う人の負担増、プライバシーの問題、二重課税の懸念などの課題も多く残っています。
今後の制度設計次第で、負担の公平性や受け入れやすさが大きく変わるため、国民の理解を得るには慎重な議論が必要です。 走行距離税が日本の交通社会に与える影響について、今後の動向が注目されます。
よくある質問
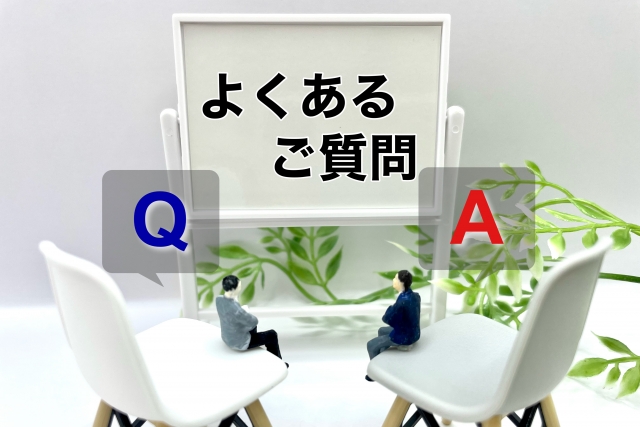
走行距離税の対象になる車は?
ガソリン税の減収を補う目的があるため、すべての車に対して公平に課税する仕組みが検討されています。
走行距離税の負担を軽減する方法はある?
制度設計次第では、地方在住者や業務利用者向けの減税措置が導入される可能性があります。また、エコカーへの優遇策が検討される可能性もあるため、環境性能の高い車への乗り換えも一つの選択肢となります。









